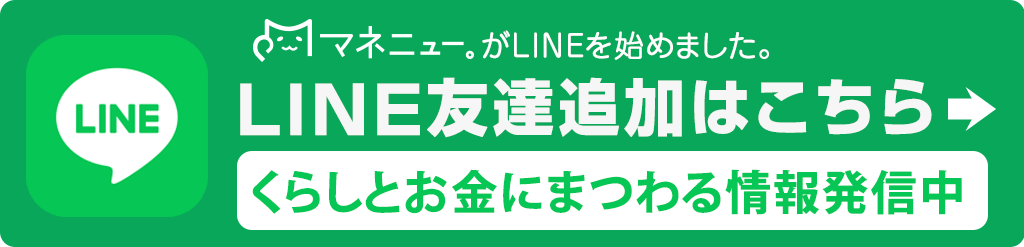※画像は生成AIを活用して作成しております。
2023年「今年の漢字」に「税」が選ばれましたが、その理由の一つとして増税に関する議論があったからと考えられています。
そこで、増税に備えるために節税の手段として金融商品の活用をいくつかご紹介します。金融商品で節税しながら将来に備えましょう!
「今年の漢字」に「税」は9年ぶり2度目!他に複数回選ばれた漢字は?
昨年12月に「今年の漢字」が発表されましたが、皆さんの予想は的中しましたか?
2023年は、法人税・所得税の増税に関する議論やふるさと納税制度の厳格化、新NISA制度などの税にまつわる話題が理由で「税」が選ばれたと考えられています。
実は「税」は、2014年にも選ばれており、9年ぶり2度目の選出だとご存知でしたか?
ちなみに、2014年は消費税が5%から8%に増税された年でした。
過去に複数回「今年の漢字」に選ばれた漢字はこちらです。
「災」2018年 2004年
「戦」2022年 2001年
同じ漢字でもその年によって起きた出来事が異なるので選ばれた理由も異なります。
気になる方はぜひ調べてみてください。
増税に備えよう!金融商品でお金を増やしながら節税も!
できることなら増税して欲しくはないものですが、今後もさまざま増税されると考えられます。
一生懸命に働いても税金によってお金が逃げていく…それなら食い止めるために正しく節税するしかありません!
個人の節税には様々な方法がありますが、今回は金融商品を活用した方法について紹介します。
所得控除制度
所得控除制度とは課税される前の所得金額を減額することで、所得税や住民税の軽減ができる制度です。
金融商品が対象の控除は「生命保険料控除」「地震保険料控除」「小規模企業共済等掛金控除」があります。
毎月の保険料や掛金を所得金額から差し引くことで、税額が少し安くなる可能性があります。
生命保険料控除・地震保険料控除

生命保険や地震保険に加入していると保険料控除を利用することができます。
生命保険料控除には「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3種類があります。
地震保険料控除は、地震保険に加入していると利用できますが、地震保険単体の商品はなく、火災保険などとセットで契約する形になります。
例)
終身保険
万が一の状況に備えながら一般生命保険料控除で節税
医療保険
病気等での出費に備えながら介護医療保険控除で節税
個人年金保険
お金を運用して増やしながら個人年金保険料控除で節税

また、医療保険や介護保険は、新制度では「介護医療保険料控除」に該当しますが、旧制度では「一般生命保険料控除」に該当します。
控除証明書に、適用制度が旧制度か新制度か、一般(生命保険)用、介護医療用、個人年金用かが記載されていますので、毎年の年末調整や確定申告で心配する必要はありません。
筆者は個人年金保険に2つ加入し、それぞれ「個人年金保険料控除」と「一般生命保険料控除」を利用しています。
小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金控除の対象となる共済契約に基づく掛金には、
「小規模企業共済の掛金」「iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金」「心身障害者扶養共済制度の掛金」があり、個人で利用できるのは「iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金」「心身障害者扶養共済制度の掛金」です。
iDeCo(個人型確定拠出年金)には、「掛金を支払っている時」「お金が増えた時」「お金を受け取る時」と3つの場合に節税効果が得られるメリットがあります。
「掛け金を支払っている時」
月々の掛金が所得控除の対象となり、所得税と住民税を軽減することができます。
「お金が増えた時」
NISA制度と同じく運用益に税金がかかりません。
「お金を受け取る時」
一時金か年金形式での受け取りを選択できるのですが、一時金の場合は退職所得控除が適用、年金形式の場合は公的年金等控除が適用されますので、いずれの場合も節税効果を得ることができます。
様々な税制メリットがあり魅力的ですが、注意すべき点もいくつかあります。
- 元本割れのリスクがある
- 運用商品として投資信託を選択した場合は、別途信託報酬が発生する
- 原則途中で引き出すことはできない(休止は可能)
筆者は今年からiDeCoを始めるために証券口座開設中ですが、iDeCoは申し込みから利用開始までに1ヶ月半〜2ヶ月半かかると言われています。
証券口座開設の審査を含めると3ヶ月近くかかる可能性があると考えて優先的に手続きした方がいいかもしれませんね。
少額投資非課税制度(NISA制度)

本来、特定口座や一般口座での運用益に20.315%の税金が課せられるのに対し少額投資非課税制度、通称NISA制度および新NISA制度は、投資商品の運用益に税金がかかりません。
また、急にお金が必要になってもいつでも換金できます。
しかし、一時的に元本割れする可能性がありますので、長期・分散投資することが推奨されています。
筆者はNISA制度のつみたて投資枠を利用して2銘柄で積立投資をしています。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

住宅借入金等特別控除、通称住宅ローン控除は、個人が住宅ローンを借り入れた場合に控除を受けられます。
借り入れてから最長13年間は所得税(場合によっては住民税も)が控除され、税額が安くなる可能性があります。
所得控除や小規模企業共済等掛金控除と異なる点として、以下2つが挙げられます。
- ローン残高の0.7%が控除額となる
- 所得金額から差し引かれるのではなく、所得税や住民税から直接控除される


ペアローンや連帯債務の場合も利用できますので、それぞれで申請しましょう。
まとめ

2023年「今年の漢字」に「税」が選出されたことにちなんで、金融商品を活用した節税についてご紹介しました。
節税には様々な手段があり、所得控除制度、小規模企業共済等掛金控除、少額投資非課税制度、住宅借入金等特別控除などが挙げられますが、これらの控除を受けられる金融商品は税制メリットだけでなく、リスクや注意点も考慮する必要があります。
皆さまのライフプランに合わせて、金融商品をうまく活用し、節税しながら資産形成していきましょう。
執筆者プロフィール
小美野 美咲子(株式会社MILIZE 金融マーケティング部所属)
神奈川県出身。FP2級を取得。
前職にて、窓口テラー、個人リテール、融資業務を経験。個人の人生を豊かにするべく、FP知識や個人リテール経験等を活かした金融の記事を執筆していく。